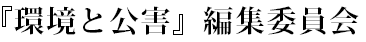『環境と公害』第53巻 第1号 2023年7月号〔最新号〕

『環境と公害』第53巻 第1号 2023年7月号 目次
| タイトル | 執筆者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| リレー・エッセイ | 原発依存・日本の危機を救え | 保母武彦 | 1 |
| 特集1 | 除去土壌・放射性廃棄物問題 | 2 | |
| 特集1 | 特集にあたって――原子力発電を廃棄の側面からみる | 大島堅一 | 2 |
| 特集1 | 事故由来放射性物質汚染廃棄物と除去土壌の再生利用――原子力政策と環境政策の複合問題として | 茅野恒秀 | 3 |
| 特集1 | 除去土壌の再生利用実証事業の問題点――所沢,新宿で起きていることから考える | 大坂恵里 | 9 |
| 特集1 | 高レベル放射性廃棄物処分をめぐる法的課題 | 下山憲治 | 15 |
| 特集1 | 高レベル放射性廃棄物処分政策の現段階と課題――「ポスト・テクノクラシー」をどう見るか | 寿楽浩太 | 21 |
| 特集1 | 寿都町・神恵内村における核ゴミの地層処分――地質条件から見た地層処分の問題点 | 岡村聡 | 27 |
| 特集1 | 最終処分場の文献調査をめぐるフレーミング分析――寿都・町民の会の活動へのさらなる連帯に向けて | 高野聡 | 32 |
| 特集1 | 《座談会》放射性廃棄物と除去土壌を巡る諸問題 | 大串伸吾・諸松瀬里奈・大坂恵里・茅野恒秀・山下英俊・大島堅一 | 37 |
| 小特集 | 中南米における環境権・自然の権利の動向 | 45 | |
| 小特集 | 環境権に関する2022年7月の国連総会決議と発展途上国 | 山崎圭一 | 45 |
| 小特集 | 進化する自然の権利訴訟――エクアドル,コロンビアにおける判例の展開 | 大久保規子・チアゴ トレンチネラ・山下英俊 | 51 |
| もう一つの原子力の町,ロヴィーサ――フィンランドにおける核のごみ処分問題の多面的理解に向けて | 中澤高師・西林勝吾 | 57 | |
| 投稿論文 | 日本の自治体におけるゼロカーボン宣言の政策波及 | 河合要子 | 63 |
| 共同声明 | 国の福島原発事故発生責任と被害賠償を求めた「いわき市民訴訟」仙台高裁判決に対する共同声明 | 研究者有志 | 70 |
第44巻以前の目次
第44巻以前の目次はこちらから参照ください。
ご購読のご案内
岩波書店の『環境と公害』ホームページから、本誌バックナンバーの注文が可能です。
定期購読会員へのおさそい
『環境と公害』は、岩波書店より年4回発行されています。定期購読の申込みは上記リンクから可能です。 第48巻第1号(2018年7月号)から価格を改定することにいたしました。定期購読会員各位には、本誌への論文投稿の資格が与えられます。
日本環境会議入会申込 (年会費一般8000円、学生5000円で『環境と公害』の定期購読も可能)
投稿論文募集のお知らせ
『環境と公害』は、年4回投稿論文を募集しています。詳細な募集要項はこちらのページ からご確認ください。
第74回投稿論文募集受付期間 2023年10月20日~2023年10月26日
『環境と公害』創刊40周年記念CD-ROMアーカイブ』について
2013年、『環境と公害』編集委員会の母体となった「公害研究委員会」は、1963年の発足から数えて50年を 迎えました。また、1979年には「日本環境会議」が設立され、2014年に35周年を迎えました。これらを記念し、 本委員会では、『環境と公害』第1巻第1号から第40巻第4号までを収めたCD-ROM版を制作し、 2014年6月27日に刊行いたしました。
2002年にも、『『環境と公害』創刊30周年記念CD-ROMアーカイブ』を制作いたしましたが、今回は収録する 論文を10年分追加するだけでなく、30周年版にはなかった全文検索機能(一部はOCRデータによる簡易検索)を 付加しております。
編集委員会からのお知らせ
本誌49巻2号掲載の土井論文に関する著者による訂正とお詫び
本誌50巻1号の表紙に関する編集委員会からの訂正とお詫び
編集顧問・編集代表・編集同人・編集幹事
- 顧問
宮本憲一 - 編集代表
淡路剛久/寺西俊一/原科幸彦 - 編集同人
淡路剛久/石倉研/磯崎博司/礒野弥生/井上真/氏川恵次/大久保規子/大倉茂/大坂恵里/大島堅一/大森正之/尾崎寛直/窪田亜矢/佐無田光/島村健 /下山憲治/高村ゆかり/茅野恒秀/辻内琢也/寺西俊一/永井進/中島直人/中地重晴/中村剛治郎/西村幸夫/羽島有紀/長谷川公一/羽山伸一/原科幸彦/保母武彦/堀畑まなみ/宮本憲一/村山武彦/山崎圭一 /山下英俊/除本理史/吉村良一/リック・デーヴィス